
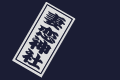
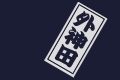
|
神田同朋町の歴史について この界隈は、かつて同朋町(どうぼうちょう)と呼ばれていました。同朋町の範囲は、現在の町名では外神田二丁目10~15番地と、蔵前橋通りをはさんで外神田六丁目1、2、3番地の辺りに相当します。(地図上では神田明神のお膝元、こちらのエリアとなります)  [ 蔵前橋通りの看板 ] 江戸時代の初めごろまで、神田神社にほど近いこの地区は、大きな寺が立ち並ぶ寺社地でした。ところが、「明暦の大火(振袖火事)」(明暦三年・1657)によって、神田一帯は焼け野原になってしまいます。 翌年、幕府は本格的な江戸の再開発に乗り出しました。その際、神田神社の裏門周辺は、御坊主衆の屋敷地に指定されたのです。さらに寛文十年(1670)には、町内に商人や職人が住む町屋も生まれています。 御坊主衆とは、江戸城内で将軍や大名など、身分の高い武士につかえた法体姿の案内世話役のことで、同朋衆とも呼ばれました。彼らのおもな仕事は、江戸城内の案内や茶、弁当の手配などでした。将軍が外出する際は、長刀をもって従ったそうです。 四人の上役を同朋頭(200石高)といい、この四人だけが将軍や老中、若年寄の用事を担当し、それ以外の御坊主衆は大名たちの用事を務めたとされています。 また、「南総里見八犬伝」で有名な曲亭馬琴(滝沢馬琴)は、文政七年(1824)、九段中坂からこの同朋町に移り、天保七年(1836)までこの町の住人でした。 上記本文は「千代田区 町名由来板ガイド 同朋町篇」を引用させて頂きました。 尚、明治以降も日本を代表する文豪の作品に、同朋町の名が刻まれております。(太宰治:東京八景、芥川龍之介:戯作三昧等) |